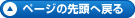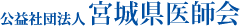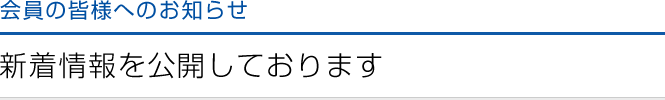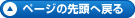- HOME>
- ��t����̊F�l�ցb����̊F�l�ւ̂��m�点
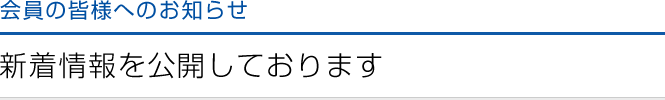
2011/04/21�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�iH23.4.21�Łj
�����{��t��������������
�@���{��t��̌���������V�鏑�ے��A���c�L��E���ے���Ƌ��ɖ{���K�₳��A�{�錧�ɂ�����ЊQ�̏ⓖ��̑Ή��A����̑Ή��̌o�߁AJ-MAT�̊����Ȃǂɂ��Ĉӌ��������s���܂����B�{���͈ɓ���A�Ð�����A���{��C�������Ή����܂����B������͂��̌�A�{���C������`���ɔ�������A���̂܂܊�茧�Ɍ������܂����B
����29��{�錧��t���C������i�k�Њ֘A�j
�P�D�܂��A������������A���ꂽ�B������̔����͈ȉ��̒ʂ�B
�u���͔��Ќシ���ɔ�Вn��K�₵�����A���̉������s�����Ă���Ɗ������B�܂��������̂̉ߏ��]����A�u�������v�̖����̍\���ɂ͓{���������B�����������AJ-MAT�͔������ɂ����Ă͖������ł͂��������A���ݑ����̃`�[�����������ł���B�_�˂̐k�Ђł́A��8���~�̌��I�ȕ����������g��ꂽ���A����͂��̐��{���K�p���Ɗ����Ă���B���Ў��Ɍ��n�ő����̂���̂����̂܂܂ɂȂ��Ă���̂����āA���{�ł��̂悤�Ȏ����N���ėǂ��̂��Ǝv���܂��o�Ă����B���n�̈�t��̕����Ɍh�ӂ�\����Ƌ��ɁA���������Ƃ��x�����p������̂ŁA�v�]������Ή��ł������ė~�����v
�Q�D�Ɩ����S�ɂ������
�����i�a�j��C�������A4��15���i���j�ɓ���̒��앛��A��؏�C������Ƌ��ɁA�u�Ð�A�Ί��A�Տ�����@�����������ꂽ�i4��18���Ńj���[�X�ŕς݁j�ȏ�̏ڍׂ́A5��5�����̓���j���[�X�Ɏʐ^�Ƌ��Ɍf�ڗ\��ł���B�Ȃ������u�Ð�a�@�̓��@�@�\�́A���o�Ďs����˂�ܕa�@�Ɉړ]�����v��ł��鎖���A�͖k�V��ŕ���Ă���B
�R�D����23�N�x���k�n�������m���n�k�ɂ�����ЊQ���������i��Ñݕt�j���̉���
���{��t����A�Ɨ��s���@�l������Ë@�\���s������23�N�x���k�n�������m���n�k�ɂ�����ЊQ���������i��Ñݕt�j���ɂ��āA�{�N4��1�����琧�x�̉��肪����A��Ñݕt�ɂ��ċ@�B�w���ւ̑ݕt�̐V�ݓ��A�����ݕt�ɂ��ėZ�����̈����グ�₻�̑��̐��x�̌��������s��ꂽ�|�̒ʒm���������B���Y���x�̏ڍy�эŐV���A�����ɂ��Ă͉��LURL���Q�Ɗ肢�����B
http://hp.wam.go.jp/home/topics_list/recovery/tabid/947/Default.aspx
�S�D�i���j�J�Еی����Z���^�[���s�������^�]�����ݕt���x�̎��{
���{��t����A�i���j�J�Еی����Z���^�[�iRIC�j�̎��Ƃł���u�����^�]�����ݕt���x�v�ɂ��āA����23�N�x�̎��{�ɂ����蓌�k�n�������m���n�k�ɂ��r��Ȕ�Q�����n��Ŕ�Ђ����_���Ë@�ւɑ��D��I�ɑݕt�����{����|�̒ʒm���������B
�ڍׂɂ��ẮARIC�e�n������������_���Ë@�ւɑ��Ē��ڈē����邱�ƂɂȂ��Ă���B
�T�D��ʋ~��җp�ЊQ������҈�Ã}�j���A��
���{��t����A���{�V�N��w��쐬�̕W�L�}�j���A���̔z�z�˗�������A�ߓ����ɌS�s��t��֑��t���邱�ƂɂȂ��Ă���B
�{�}�j���A���́A�Q�֘A����h�����߂ɑ��������A���Â��d�v�ł���A��ÊW�҂̑��A���̍���҂��x����Ƒ��A��ʋ~��҂̕��X�ȂǍL���ڂ�ʂ��Ă��������邱�ƂŁA���ɂ����鍂��҂̌��N�Ǘ��Ɏ�������̂ł���B
�U�D���Ҏ��ꑊ�k�����ē��`���V
���k����l�b�g���[�N���A����̑�k�Ђɂ����鉈�ݔ�Вn�̑����̂��҂��f�Â��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ă��邱�Ƃ���A�L�����k���������m����ړI�ŕW�L�`���V�̔z�z�˗�������A�S�s��t��֑��t���邱�ƂɂȂ��Ă���B
�V�D���k�n�������m���n�k�ɂ��{�錧��t��ݏ���ЊQ�������ɂ���
����̒n�k�ɂ��{��ݏ������ւ̍ЊQ�������̋�̓I�Ȏ戵�����������肵�A�e�S�s��t��֒ʒm���邱�ƂɂȂ����B
�������V���Ђ���ы����ʐM�Ђ���̎��
4��20���i���j�ɒ����V���Ђ̒ҁ@�O�L�q�L�҂���ы����ʐM�Ђ̕x�c���S���L�҂��{�錧��t��ق�K��A��k�ЂɊւ���{�錧��t��̎��g�݂Ȃǂɂ��Ď�ނ��܂����B�����͍����i�a�j��C�������Ή����܂����B
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��21���i�j���̑�����ː��ʂ�0.11μSv/hr�Ƃقڒʏ�l�Ō��N�ɂ͉e���̂Ȃ����x���ł��B
2011/04/18�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�iH23.4.18�Łj
����26�����(�k�Њ֘A����)
�P�j ����A�@�����\�z�ɂ���
�Q�j �S����t�����g���A�����22�N�x��4����
4��10��(��)�ɊJ�Â���A�����{��k�Ђً̋}�x����ɂ��ċ��c���s��ꂽ�B�{���́A�ɓ�����o�Ȃ����B
�R�j �����{��k�ЂɊւ���A���P�[�g�����ɂ���
�����{��k�Ђɂ�����e��Ë@�ւ̔�Q�i�l�I��Q���тɕ��I��Q���j�A���Ў�����̐f�Ï��Ë~�슈���̏A���_�ƌ���̗v�]���ɂ��Ē������s���A�����x�������������ł̊�b�����Ƃ���ƂƂ��ɁA����̍ЊQ��ɖ𗧂Ă邱�Ƃ�ړI�ɑS��Ë@�ւ�ΏۂƂ����A���P�[�g���������{����|�̕��������B
�S�j�@�e�n��̍ЊQ�Ή��i�������j�ɂ�����ۑ�A�j�[�Y�A�Ή����j�Ȃǂɂ���
���X�i�~�j��C���������������
�T�j�@��124����{��t�����c����ɂ������\����y�ьl����ɂ���
��������t����\����A��������t��A�{�錧��t��A��茧��t���e�P��̌l���₪�\�肳��Ă���B�{�錧����͉Ð�������s���B���e�͑S�đ�k�Њ֘A�ƂȂ��Ă���B
������L��ψ���̊J��
4��14��(��)�ߌ�3������W�L�ψ���J�Â���܂����B�{�錧��t���͍����i�a�j��C�������s�u��c�ŏo�Ȃ��܂����B�ψ���ł́A��Ƃ��đ�k�Њ֘A�̎����b��ƂȂ�܂����B�{�錧����́A�e��t���̎x���ɑ��銴�ӂ��q�ׁA����ƍ���̉ۑ�Ȃǂɂ��ďq�ׂ܂����B
������r�j���{��t���A��ؖM�F��C��������O�����A�Ί��s�A����s�Տ�����@
4��15��(��)�ɓ��{��t��̒��앛��A��؏�C�����A�㌴�ی���Éے����������A�{�錧��t���́A�����i�a�j��C�����A�蓈�����ے������s���܂����B
�悸�͓�O�����̃x�C�T�C�h�A���[�i�A�����u�Ð�a�@���ݐf�Ï������@���A�����������A��؉@���A���c���@���Ɖ�k���܂����B�����ĊJ�����f�Ï������@���A�ی��f�Â��\�ł���Ƃ̎��ł������A��Ў҂̎��ȕ��S�����̊��ԉ����Ȃǂ��A���n�ł̌o������Ɍ��������͗l�ł����B
�����ĂɐΊ��s�̓��a�R��������Ί��`�����@���A�Ί��s��t��̑C����搶�A�V�Ȏ����ǒ������Ȃ��������܂����B�X�ɖ���s���|��`�����@���A����`�����s�@�œ����ւ��߂�ɂȂ�܂����B
��Вn�����ۂɌ��āA���̎S��Ɍ��t�������悤�ł����B�����x���X�ɐi�ގ������҂��������̂ł��B
�������r���ޗnj���t�������
4��17���i���j�ɍ����x�ڂƂȂ�ޗnj���t���̉����r���搶�����ق��܂����B������͓�O������JMAT�Ƃ��Ă̈�Ë~�슈�����I���A���̕ƍ���̑Ή����x����ɂ��āA�ɓ���Ə��������s���܂����B
������́A������ޗnj��̈�Ë~��ǂ�5��14���܂ŋC����s���O�����Ŋ������s���A���̌�ɂ��ẮA�{�錧��{��ƒ������Ȃ���p���I�Ɉ�Ë~�슈�����x�����Ă��������Ƃ̐S�������t���ɓ���֓`���A�A�H�ɏA���܂����B
���{�錧���@��A�Ȉ��������s�Őf�Îx��
�ЊQ���}�������߂��A���ł̈�Ãj�[�Y���ω����Ă��邱�Ƃ���A�{�錧��t��̈˗������_�ѓ���������{�錧���@��A�Ȉ��A4��17���i���j�ɋ��{�����C�����ƂƂ��ɓ������s����s���Z���^�[�Ƒ剖�s���Z���^�[��K���Îx�����s���܂����B���̎Q���҂͓������s�̐Ί_��t�A���s�̓���@�L��t�ł����B
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��18���i���j���̑�����ː��ʂ�0.11μSv/hr�Ƃقڒʏ�l�Ō��N�ɂ͉e���̂Ȃ����x���ł��B
2011/04/13�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�iH23.4.13�Łj
����3����{��t��ЊQ���{�� �g���c
4��12���i�j�ߌ�4��������{��t��ЊQ���{����c�E�g��e���r��c���s���A�ɓ�����o�Ȃ��܂����B
�i�P�j�{�錧��t���̕�
�E�{��4��12�����݂ŁA���҂�8,017���A�s���s���҂�6,387���łƂȂ��Ă���B
�E�����܂ł̈�Ë~����̃`�[������240�`�[���ł���A4��11������101�`�[�����������Ă���B�i���i�l�`�s��37�`�[���j
�E�C����s��t����4�����܂łɁA��Ë~����������R�C�S�`�[���~�����Ƃ����˗����������B�܂��A��O���������4��������̈�Ë~����̒����h���̈˗����������B
�E�{�錧��t��P�Ƃł��A���炩�̌`�Ŏx�����������Ă���B
�E��O�����Ŋ������Ă����C�X���G���R�̈�Ã`�[�����A�ȈՌ^��Î{�݂ƈ�Ë@���u���ċA�������߁A���̋@��ނ��g���Ē����a�@�̃X�^�b�t���f�Â��n�߂�ƕ����Ă���B�܂��A��O�����̈�Ë@�ւ͑S�ł������߁A�̈�ق���i�~�쏊�j�Ƃ��Ďg�p���Ă���A���������B
�E�Ί��n��ɂ��ẮA�Ί��ԏ\���a�@���A����1�����ԑS�͂Őf�Âɓ������Ă���B
�E�e���ʂ�蒸�Ղ����`��������Ë@�ւ̑���̒��x�ɂ��A�S�s��t��֕��z�����B
�i�Q�j��茧��t���̕�
�E���҂�3,822���A�s���s���҂�4,091���ł���B
�E�����܂ł�JMAT�̃`�[������70�`�[���ł���A����12�`�[���������Ă���B
�E���������ψ���𗧂��グ�A�ΐ����ψ��Ɏw�����ꂽ�B
�E9���i�y�j�ɌS�s��t����c����J�Â����B
�@�@�@�@�u�i�l�`�s����āv�̏��������F���ꂽ�B
�E�����ł͓����n��̈�t�����ݕ��ɔh������Ƃ����Ή����������Ă���B
�i�R�j��������t���̕�
�E�����܂ł̂i�l�`�s�̃`�[������100�`�[���ȏ�ł���B
�E�������k�x�U���A�U��̗]�k�������Ă���A�����̎��̕]�����x�����V�ɏオ�������Ƃ�����A���]��Q���o�Ă���B�܂��A���{���v��I������ݒ肵���B
�E�i�l�`�s����Ў҂̉h�{�̕肪����Ă���A�s���Ɉ˗����āA�r�^�~���E�~�l������ێ�ł���悤�ȑ̐����l���Ă���B
�E�r�C�A�����ǂ̏W�c�����̕�����B
�i�S�j���{��t���̕�
�E�����܂ŁA��茧�A�{�錧�A�������ɑ��āA�S������i�l�`�s���܂߂���Ë~�����463�`�[���h������Ă���B
�E5�����܂ł͂i�l�`�s�`�[���̌p���I�Ȕh�����l���Ă���B�i�����܂ŋ��ł���A6���ȍ~�h�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�j
�E���i�Ǝ҂��A15�����x�̃v���n�u�f�Ï��̐\���o������A��茧��ƒ��ɐݒu���������Ă���B
�E���ɂ������Ў҂̐�含�̍����f�ÉȖڂ̎�f�ɂ��ẮA�܂��͊e���őΉ����Ă��������A�s�\�ł���A�i�l�`�s�`�[����h���������B
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��13���i���j���̑�����ː��ʂ�0.11μSv/hr�ƌ��N�ɂ͉e���̂Ȃ����x���ł��B
2011/04/11�F���{����u���w��v�̂��ē�
���{����ł́A����̗\�h�E�f�f�E���ÂɊւ�����I�Ȓm���ƋZ�\�����C���邱�Ƃɂ��A���f�̐��i�Ƃ����Ð����̋ςĂɊ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����u���w��v���x��݂��Ă���܂��B
���̏��w�㐧�x�́A����t�ɏ��w�����x�����A��������Ë@�ւɌ��C�����肢������̂ŁA�e�a�@�̌��C��A���W�f���g���̌`�Ō��C����]�����t�{�l�����C������܂��͊m�肵����A����Ɂu���w��v�Ƃ��Đ\������d�g�݂��Ƃ��Ă���܂��̂ŁA���ē��������܂��B
��W�v�́A�\�������͂�����
2011/04/11�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�iH23.4.11�Łj
���N��@�[�@��������b�Ƃ̍��k��
��L���k�����23�N4��9��(�y)17�F00����{�錧��t��قōs���܂����B
�o�ȎҁF�N��@�[�@��������b�E�Q�c�@�c��
�{�錧��t��—�Ð��A�N�䗼����A���{�A�����i�a�j�A�o�Ċe��C����
���s��t��-�i���A���A���䗼����A�����A����A���e����
���k��w−�������k��w�a�@���A�r�䕛�@���A���d�~�A�C�염����
�@�@�@�@�i�ɓ��{�錧��t��͈�t�����g���̐k�Б��c�̂��ߓ����o�����j
�P�D���A
������F
�E�S����Ë@�ււ̑S�ʓI�ȕ⏕�����肢�������B
�E�n���ÍĐ�����̗L���Ȋ��p���B
�E��t��݂̊Ō�X�e�[�V�����A�Ō�w�Z�ȂNJ֘A�{�݂ւ̕⏕���Ȃǂ̔z�����A���肢����B
�N�䕛��b
�E��t��Ȃǂ𒆐S�ɁA�ЊQ�ɑΉ��������ւ̎ӈӁB
�E�Ί��ł͂R���̂P�̈�Ë@�ւ��p�~�̊�@�ɂ���ƕ����Ă���B�܂��A���錤�C�a�@�@�@�ł́A�����̌��C�オ���O�ɋ������Ƃ������Ă���B
�E�m���Ƃ��b���������A����͒n�k�݂̂łȂ��Ôg�Őr��Ȕ�Q�ɂ����Ă���̂�����A��_�W�H��k�Ђ̎��Ɠ�������x�o�i�����͂R���̂Q�A���Ԃ͂Q���̈�j�ł͑ʖڂ��ƍl���Ă���B
�E���I�̓P���͈ꕔ�����n���S���������A����͑S�z����ł��B�n�������̂ɕ��S�͂����Ȃ��B
�Q�D���ЈȌ�̑Ή�
�{�錧��t��i���{��C�����j�A���s��t��i�i���j�A���k��w�i�����a�@���j���A���ЈȌ�̊e��t��A��w�̑Ή��ɂ��ĕ��������B
�R�D��Q�̏ƕ����\�z
�����e�n�̐l�I����ю{�݂̔�Q�̏ɂ��č�����C�������������������B
�S�D�ӌ�����
�@�N�䕛��b����
�E��t�i���ю�j���S�̏ꍇ�́A�T�S���~�̒��ԋ��B���ю�ȊO�̎��S�͈�l250���~�̒��ԋ��B�S��̏ꍇ�́A�P�Ƒ��ɕS���~�B����̏ꍇ�́A50���~�B
�E�Č�����ꍇ�A�S��̏ꍇ��200���~�B����̏ꍇ��100���~�B�����x���̑ݕt�i�T�N�ԕԊҗP�\�j��350���~�B�����ꏊ�ōČ�����l�ɂ́A�ȑO�͗\�Z�͏o�Ȃ�����������͕ʂƍl���Ă���B
�E�x�ƕ⏞�i�E���j���Ǝ蓖�̊��ԉ�����������
�E�@�l�ł̊ҕt�ɂ��Ă��������ł���B
���̌�A��Вn�̈�Ò̐�������ǂ�����̂��ɂ��ē��_���s��ꂽ�B
�E���Ƃ��A��Ã��[���A���c�Z��A���X�X����̂Ƃ��čl�����Ȃ����B
�E�Ί��s���a�@�̍Č����ǂ��l����̂��B�܂������u�Ð�a�@�̍Č����ǂ�����̂��B�]���̂悤�ȁA�n��̗v�]�������ł͑ʖڂł���B�s�����̗v�]���]���̃X�^�C���ł͂Ȃ��A�a�@�̗L���Ȕz�u���ǂ�����̂��ȂǁA���̍ۃO�����h�f�U�C�������߂鍇����c�Ȃǂ��K�v���B
�E���ԕa�@�̕⏕�͂ǂ�����̂��B������̕⏕�̏���͗Ⴆ�Γ��ԕa�@�ł��Q���̈ꂾ�B����ȏ�͂ǂ����낤��?�s�������炻�̖��ԕa�@���A�����Ƃ��Č����a�@���݂ł���Ƃ����v�]�����n������o��Ό��I�a�@�ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�E�l���f�Ï��̏ꍇ�A��_�W�H�̏ꍇ�͉��ݐf�Ï��i�Q�N�Ԃ̎����Łj�ɖ�1000���~�̕⏕���o���O�Ⴊ���邪�A������l���Ă��炢�����B
�E�l�ōČ�����ꍇ�̕⏕�́A���������Q���̈ꂾ�i����j�B�l�ւ̕⏕�͓���ʂ����邪�A�����S�z���S���Ĉ�Ã��[����A�����ň�Ê��������Ē������Ȃǂ́A���Ƃ��Ă͉������₷���B
�E���C�オ���k���瓦�U����\��������B�����h�����@���l����ׂ����B
�E���{�݂̗����A�S��Ȃǂ��l�����ׂ���肾�B
�E��������������ɁA�a�@�̓��p�����i�މ\��������
�ȏ�̂悤�ɁA�F�X�ȋc�_���o�܂������A����e��ÊW�c�́A�s�����A�����Ƃ���̂ƂȂ�A���̍��������o��Ƌ����������߂��Ă���Ƌ��������܂����B
�Ȃ��ȏ�͕������ł���A���Ƃɋx�ƕ⏞�A�ٗp�����������Ȃǂ̏ڍׂɂ��ẮA�ēx���̕��͂�����c���̎������ɑ���Ċm�F����\��ł��B
�����Ɍ���t��A���Ɍ��Y�w�l�Ȉ��{�錧��t���K��B
�@
���Ɍ���t��̓c����C�����ƕ��Ɍ��Y�w�l�Ȉ��̑哇�������23�N4��9��(�y)12�F30�ɖ{���K�₵���B���{��C�����Ə��i���Y�w�l�Ȉ���C�������Ή������B
���e�͐Ί��n��ɂ������Îx����������ю��Y����Âɂ��Ă̈ӌ������ƁA���Ɍ��Y�w�l�Ȉ���̎x���̌����ł������B
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��11���i���j���̑�����ː��ʂ�0.15μSv/hr�Ō��N�ɂ͉e���Ȃ����x���ł��B
2011/04/08�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�iH23.4.8�Łj
���ő�]�k�ւ̑Ή�
4��7���i�j�ߌ�11��32�����A�{�錧���i�k��38.2�x�A���o142.0�x�A���������̓�40�����t�߁j��k���Ƃ��A���s�{�����I���s�Ők�x6�����ϑ�����n�k������܂����B�k���̐[���͖�40�����A�n�k�̋K�́i�}�O�j�`���[�h�j��7.4�Ɛ��肳��Ă���܂��B
�n�k��������A�ߌ�11��50���߂��ɂ͌���t��قɓo�ď�C�����A�����Lj���������U�W��������A�o�ď�C�����͋{�錧�ЊQ���{���ցA�����Lj��͈ɓ���Ƃ̘A���A��ق̔�Q�������s���ƂƂ��ɁA�l�b�`�����A�d�b�A���[�����O���X�g���Ŋe�n��̔�Q�̊m�F��A���s��t��A�{�錧�ی���������Ð����ہA����ÃZ���^�[���Ƃ̘A�������ɂ�����܂����B
�o�ď�C�������A�����ʼn���l���o�Ă���Ƃ̏�������܂������A�r��Ȕ�Q���Ȃ����Ƃ��m�F���A�{��8���i���j�ߑO2��30���Ɉꎞ���U�ƂȂ�܂����B
8���i���j��������e�S�s��t��ւl�b�`�����A�d�b���ɂĐV���Ȕ�Q�̊m�F�Ə����W�ɂ������Ă���܂��B
��������������A���k����֓��ɂ����Ă̍L���͈͂ŋ����]�k����������\��������Ƃ�������Ă���܂��̂ŁA�搶���ɂ�����܂��Ă��]�k�ւ̌x���ƈ��S�m�ۂ̂����A�f�Âɏ]���肢�܂��B
��28���C������i4��6���j�ɂ�����k�Њ֘A�����̕�
���ɓ�����A
���݁A�}�������疝�����Ɉڍs�����邪�A�x�������i���i�j�̕��z���@��~�����i��t�̔h���Ȃǁj�̑̐��č\�z�̎����ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ̌����������ꂽ�B
���Ɩ��������S��
��O�����A���n��A�Ί��n��A�����n��ɂ�������e��C����������ꂽ�i��O�����̓̕j���[�X7���łɌf�ڍς݁j�B
���ی��W�͐f�Õ�V�����̎�舵���ɂ���
���{��t����тɓ��k�����ǂ��ʒm��Q&A�ƂƂ��ɔ��o����Ă���A�d�v�Ǝv����B������j���[�X7���łɌf�ڂ��Ă���A�e�S�s��t��ɂ����t�����̂ŁA����ւ̎��m���X�������肢�������B�Ȃ��^��_�Ȃǂ́A���̓s�x�{�錧��t��ɊĒ�����A���k�����ǂȂǂƂ����c�������B
���{�錧��t��ݏ���ЊQ�������̎�舵���ɂ���
���ʂ̓��k�n�������m���n�k�ɂ�����{��ݏ���ЊQ�������̎戵���ɂ��ċ��c���s��ꂽ�B
���{�錧��t�����E��Ë@�֓������E�x�����k�����̐ݒu�Ɍ�����
����̑�k�Ђɂ�����{�����A��Ë@�֓��̕����x�������ݒu�Ɍ����ċ��c���s��ꂽ�B���k��w�Ƃ����c���Ȃ���i�߂�\��ł���B
���e�n��ɂ�������Ȃǂ̕ی���Õ��������ɌW��ӌ�������
���݁A�{�錧�ی��������̌Ăъ|���Łu�e�n��ɂ�������Ȃǂ̕ی���Õ��������ɌW��ӌ�������v������5�n��ŊJ�Â������B�Q�W�҂́A�ی������A�e�n��̕ی������S���ҁA���q���S���ҁA������ъe�n��̍ЊQ��ÃR�[�f�B�l�[�^�[�A���ЊQ�ی���ÃA�h�o�C�U�[�A�S�s��t��A���Ȉ�t��A��t��ƂȂ��Ă���B
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��8���i���j���̑�����ː��ʂ�0.1μSv/hr�ƕ���̃��x���ɖ߂�܂����B
2011/04/07�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�i4��7���Łj
�����k�n�������m���n�k�Ȃǂɂ��e���܂��� �Z�[�t�e�B�l�b�g�ۏi5 ���j�̑ΏۋƎ�̊g��ɂ���
���{��t����A�W�L�ɂ��Ēʒm������܂����B
���ʁA���k�n�������m���n�k�Ȃǂɂ��e���܂��A������ƒ��́A�i�C�Ή��ً}�ۏؐ��x���I������{�N4������A�Z�[�t�e�B�l�b�g�ۏi5���j�ɂ��ẮA�ً}���I�ɁA����23 �N�x�㔼���ɂ����āA�u��ËƁv�����łȂ��A�u�Љ�ی��E�Љ���E��쎖�Ɓv�A�u�ی��q���v�����܂ތ����S�Ǝ�ł���82�Ǝ�œ����x���^�p���邱�ƂƂȂ�܂����B
�����k�n�������m���n�k�Ȃǂɂ��e���܂��� �Z�[�t�e�B�l�b�g�ۏ�
�i5���j�̑ΏۋƎ�̊g��ɂ���
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/22nen_61.pdf
�����k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�ɂ���Ђ��ꂽ����҂̔����ɂ�������T�[�r�X�̊m�ۂɂ��āi���W�j
�����J���Ȃ͔�Ђ��ꂽ����҂̕��X�ɑ��A�����ɂ����Ă��K�v�ȏ�����A�K�v�ȉ��T�[�r�X����邽�߁A�k�ЂɊ֘A����e�펖���A�����܂Ƃ߂����[�t���b�g���쐬�������܂����B
�{���[�t���b�g�͎����̂�ʂ��Ĕ����Ő�������Ă��鍂��҂̕��X�֔z�z����邱�ƂɂȂ��Ă���܂��B
�����k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�ɂ���Ђ��ꂽ����҂̔����ɂ�������T�[�r�X�̊m�ۂɂ��āi���W�j
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/23kai_5.pdf
����O�����u��x�C�T�C�h�A���[�i�K��iH23.4.2�j��
4��2���i�y�j������C��������O�����u�Ð�x�C�T�C�h�A���[�i�����@���܂����B���e�ɂ��ẮA���̂Ƃ���ł��B
�x�C�T�C�h�A���[�i��Ó����{�������t�Ɩʒk
��ÊW���
• �����T�P�i�u�Ð�22�A�ˑq9�A���J4�A�̒�14�A�o��2�j�A���Ґ��V�A�U�W�T�l
• ��É����`�[���Q�W�A�n����t4�l�A�ی��t�A�o�ĕی��t
• �N���X�^�[�~�[�e�B���O���T���j��15���J�Ái�e�`�[���Q���j
• �������ꌚ�ݒ��i�ꕔ�ғ��J�n�j
������{���g�D
• �{���ӔC�ҁF���V��t
• �{���w���F�����t
• �{���w���⍲�F�������`�[��
• �T�[�x�C�����X�`�[���F���m�ڑ�w
• ��Õ����Ǘ��F��������A
• �{�������F�R����w
• �ЊQ��ÃA�h�o�C�X�E�~�쏊�S�ʊǗ��FHuMA(humanitarian medical assistance)“�����c���@�l�ЊQ�l�������x����”
��݈�Ë~�쏊
�{���G�������`�[���A�C�X���G����Òc�A�Љ�ی��a�@�`�[���i���f�ԗ��������݁j
1. �x�C�T�C�h�A���[�i�GTMAT�i���B��j�A�R������t��
2. �u�Ð쏬�w�Z�G������t
3. �u�Ð쒆�w�Z�G�Q�n���`�[���A�N�c��t�i4��3���`�j
4. �u�Ð썂�Z�G�_�˒����s���a�@�A����������CL
5. ���J���w�Z�G���m�`�[���A���l�실�ρA��t�i���{��t��h���j
6. �̒Ò��w�Z�G�ޗnj���t��A�R����w�i�����Ȉ�t1�l�@4��2���܂Łj
7. ��
�������̔����ɖ��Ȃ�;�O���D���p�̖ŋۂ��ꂽ���j��E�s���Z�b�g�̃Z�b�g���~�����i�I�[�g�N���[�u�������Ȃ����߁G1��2�Z�b�g���x�j�A�T1�����I��×p�����̕�[��]
�����͓��ԂŒ����Ï���E�S�̃P�A�`�[��������{
���m���E�C���X�̈ݒ������s
���C���t���G���U���s�͏I���̕���
�����k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�Ɋւ���f�Õ�V���̐����̎戵���ɂ��āi����2�j�����o
���{��t����A�W�L�ʒm�������J���ȕی��Lj�Éۂ�蔭�o���ꂽ�|�̒ʒm������܂����B�{��Ƃ��Ă�����23�N4��7���t�ɂČS�s��t��ւ��m�点���Ă���܂����A��Ϗd�v�Ȓʒm�ł��̂ʼn��LURL���炲�m�F�����肢���܂��B
�����k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�Ɋւ���f�Õ�V���̐����̎戵���ɂ��āi����2�j�i���{��t��F��9�FH23.4.4�j
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/hoken/110311eq65.pdf
�����k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�Ɋւ���f�Õ�V���̐����̎戵���ɂ��āi����2�j�i����23�N4��1�� �����A�� �����J���ȕی��Lj�Éہj
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/hoken/110311eq66.pdf
�����k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�ɌW���ی��ҏؓ��̎戵�����ɂ��āi�p���`�j
���{��t����A�����J���ȕی��Lj�Éۂ��p���`�������ꂽ�|�̒ʒm������܂����B�{��Ƃ��Ă�����23�N4��7���t�ɂČS�s��t��ւ��m�点���Ă���܂����A��Ϗd�v�Ȓʒm�ł��̂ʼn��LURL���炲�m�F�����肢���܂��B
�����k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�ɌW���ی��ҏؓ��̎戵�����ɂ��āi���{��t��F��11�FH23.4.5�j
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/hoken/110311eq67.pdf
�����k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�ɌW���ی��ҏؓ��̎戵�����ɂ��āi����23�N4��2�� �����A�� �����J���ȕی��Lj�Éہj
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/hoken/110311eq68.pdf
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��7���i�j���̑�����ː��ʂ�0.14μSv/hr�Ō��N�ɂ͉e���Ȃ����x���ł��B
2011/04/04�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�i4��4���Łj
���x�ǐ��Ɣj�����̊��ҕ�
���s���a�@�̑�됳�q�搶����̏��ł��B�ȉ����p���܂��B
�����̓��@�~���~�}�Z���^�[�~�[�e�B���O�ŁA��Вn����x�ǐ��Ɣj�����̊��җl������������@���Ƃ̕�����܂����B
�x�ǐ��͐Ö������ǂŁA�G�R�m�~�[�nj�Q�ɂ����̂�������܂���B
�j�����́A��В���̎ł͂Ȃ��A����̕Еt���Ȃǂŕ������A���Ȃǂ��\���łȂ��������߂ɔ��ǂ����\��������܂��B
��Еt���̍ۂ̎葫�̕ی�ƁA������̐��A������f�Ŕj�����g�L�\�C�h���^�Ȃǂ̑K�v�Ǝv���܂��B
���ꂼ��̒n��ł̑Ή�����낵�����肢�v���܂��B
�����{��t��k�n�������m���n�k���i�Čf�j
���{��t��z�[���y�[�W�i�{��z�[���y�[�W������A�N�Z�X�j�œ��k�n�������m���n�k�Ɋւ���ی��f�ÊW�ʒm�ȂǗl�X�ȏ�f�ڂ���Ă���܂��B
�Ȃ��A�S�s��t��Ăɂ͒ʒm���͂����������Ă���܂����A�e�n��̏��Ԃ�����������̐搶���܂ŏ�`���Ȃ����Ƃ�����܂��̂ŁA�{����傢�ɂ����p�肢�܂��B
���{��t��k�n�������m���n�k����
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/index.html
�����k�n�������m���n�k�ɌW��ЊQ���������i��Ñݕt�j���ɂ��āi�Čf�j
���{��t�����A�W�L�ɂ��ēs���{����t����ɒʒm�����o����܂����̂ŁA3��31���t�ɂČS�s��t��ɒʒm���Ă���܂��B
�Ɨ��s���@�l������Ë@�\�z�[���y�[�W�ł��������������܂��B
http://hp.wam.go.jp/home/topics_list/recovery/tabid/947/Default.aspx
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��4���i���j���̑�����ː��ʂ�0.16μSv/hr�Ō��N�ɂ͉e���Ȃ����x���ł��B
2011/04/02�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�i4��2���Łj
���ЊQ�����`�����ɂ���
���ʂ̓��k�n�������m���n�k�ɔ������{��t������߂Ƃ��鑽���̈�t��⏔�c�̂���{��ɋ`���������Ă���A3��30���i���j�J�Â̑�27��{���C������ɂ����āA�����ł����Ɉ�Ë@�ւ̔�Q���傫�������S�s��t��ɑ��āA����������ЊQ�������F�O����Ӗ��ŋ`�����������肷�邱�ƂɂȂ�܂����B
�������s�A�����l���K��ɂ���
4��1���i���j�ɓ���A�Ð�����������s�A�����l����K�₵�܂����B
�悸�{�錧������t���K��A�{���C�����ł����鉡�R�`����֍ЊQ�����`��������n���A����̔�Q�ɂ��ĕ��܂����B���̌�A���R����s�̂��Ɣ�Q���傫��������Ë@�ւł��鑽���s�̐剖�����a�@�̗�ؗ������Ɩʒk�A���@����30�l�ȏ�̎��Â��p�����A��Еt���������I���Ȃ����A�ė��i��̂݁j���ĊJ���Ă���܂����B
�����āA�����������s�̎��ƈݒ��ȓ��Ȉ�@��K�₵���ƍh��@���Ƃ�����܂����B�f�Ï���1�K�̂��Ȃ�̍����܂ŒÔg�������S���Ǝv�����Q�ł����B
���̌�A�����l�������K��n粑P�v�����Ɩʉ�A��Q�̐�������i�̋����A�~�슈���ɂ��Ă��b���f�����܂����B���ꂩ��͌��n�̔��ŋ~���S�����Ă��� �����ܓc���N���j�b�N�̎����N�@������������A�����̔��ł��鎵���l�����������ٕ��тɏ����l���w�Z��K�₵�܂����B���ň�Ë~�슈�����s���Ă���R����DMAT���тɋ{�茧JMAT�̕��X�����Ë~�슈���̕��A�ɓ�������ӂƈԘJ�̈��A�����܂����B
���ɑ����s�̔��ł���V�^���w�Z��K��A�����Έ�@�̔�n�ޓގq�@��������ł̈�Ë~�����҂̌��N��ԁA���ɃC���t���G���U�������o�n�߂�����͏\���ł���Ƃ̐������܂����B
����̒n�k�ƒÔg�������炵����Q���z���ȏ�̑傫�����������Ƃɋ����ƂƂ��ɁA��������������ł���悤�F��Ȃ���̋A��ƂȂ�܂����B
���ЊQ�����`�����𓍐��S��t��A�Ί��s��t���
4��1���i���j�n�������ǒ�������Ɩ������Ƌ��ɐΊ��s��t����тɓ����S��t���K��A�ЊQ�����`�����ڎ�n���܂����B�i�{�錧������t��A�����S��t��A�Ί��s��t��ȊO�̔�Вn�S�s��t��ւ�4��1���t�ő����ρj
���̌�A��O�����̔��ł���x�C�T�C�h�A���[�i�֑����^�сA�~�슈�����s���Ă�������u�Ð�a�@�̗�؉@������v�]�̂��������߂�p���X�I�L�V���[�^�[�E���f��Ȃǂ̈�Ë@��ށA���i�������͂����܂����B
�����{��t��k�n�������m���n�k����
���{��t��z�[���y�[�W�i�{��z�[���y�[�W������A�N�Z�X�j�œ��k�n�������m���n�k�Ɋւ���ی��f�ÊW�ʒm�ȂǗl�X�ȏ�f�ڂ���Ă���܂��B
�Ȃ��A�S�s��t��Ăɂ͒ʒm���͂����������Ă���܂����A�e�n��̏��Ԃ�����������̐搶���܂ŏ�`���Ȃ����Ƃ�����܂��̂ŁA�{����傢�ɂ����p�肢�܂��B
���{��t��k�n�������m���n�k����
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/index.html
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��2���i�y�j���̑�����ː��ʂ�0.17μSv/hr�Ō��N�ɂ͉e���Ȃ����x���ł��B
2011/04/01�F�{�錧��t��ЊQ���{���j���[�X�i4��1���Łj
�����i�Ȃǂ̕��i�˗����@�ɂ���
���i���̕��i�˗����@�ɂ��āA3��31���t�ŌS�s��t��֒ʒm�o�����̂ŁA�����ɂĕK�v�Ȉ��i��������Ώ���̎葱���ɂāA���\���݊肢�܂��B
�葱�����ł��s���ȓ_������A�{��͋{�錧�ی��������ۂ܂ŁA���⍇���肢�܂��B
�{�錧�ی��������� TEL 022-211-2652����022-211-2653
�����{��t��ЊQ���{����c�E�g���c�i�ڕ�j
3��29���i�j�ߌ�4��������{��t��ЊQ���{����c�E�g��e���r��c���A���{��t��ЊQ���{�����ł��錴���������������ߓ��k6����t��A��錧��t����e���r��c�V�X�e���ōs���܂����B
�E��茧��t���̕�
���S��3242�l�A�s����4654�l�B��380�ӏ��A����43000�l�B����܂ŁA�����`�[���̂ق��AJMAT37�`�[�����x�������{�B3��19���A���ォ��11�n��Ɉ��i��A�B������@�ɁA���ݕ�4�J���Ɂu���i�T�v���C�Z���^�[�v��݂��A����̋������s�����ƂƂ��Ă���B�����E���ẮA����154�l�̈�t���]�����A3087�̂��I���B�ˑR�A�����̂悤�Ɉ�̂���������A�s���ґ{���������Ă���B4���ȍ~�A�p��������Â��l�����A����JMAT �ɉ����Ċ�茧��t��ł��uJMAT ���v�Ƃ��Ď��O�̃`�[�������B
�E�{�錧��t���̕�
���S��6455�l�A�s���Җ�7050�l�B��399�ӏ��A����6��6500�l�B��Q������������O�����ł́A�B��̕a�@��6�̐f�Ï����S�ŁB�C����ł́A�X�̔�������ŏ�Ԃł���A�J�Ɛf�Ï�36�{�ݒ�30�{�݂������ꂽ�B���Ґ�����ԑ����Ί��s�ł́A�X�̔����������Ȃ���ԂŁA�J�Ɛf�Ï�75�{�ݒ�28�{�݂������ꂽ�B����̎��S�͊m�F���ꂽ�͈͂�9�l�B��Q�͍L�͂ŁA�J���e�Ȃǂ������B���ł̓C���t���G���U�����s���Ă��Ă���A�ً}�ōR�C���t���G���U��A�ȈՌ����L�b�g��z�z�B
�E��������t���̕�
���S��996�l�A�s���҂�5000�l��B�����̖�肪��������A�����̕s���E�^�O�������B���̉e��������A���O�ɔ���Z���������B
�E��錧��t���̕�
�����̎����҂͏o�Ȃ��������A�C���t���̔j�Ђǂ��A�������j������5���ˁB���܂�JMAT7 �`�[���̎x���������A4���ȍ~�͎����ŕ�����i�߂�\��B�uJMAT �̗͂𑼂̓��k3���ɐU������Ă��炢�����v�Ɨv�]�B��Вn������̓��@���e������鏀�������Ă���B
�E�X���A�H�c���A�R�`���e��t���̕�
��Q�r���3���̎x���`�[�������ꂼ��`�����A�x���ɓ����Ă��邱�ƁA���͊��ҁE���@���҂̎���Ȃǂ̋��͂�B
�E���{��t���̕�
3��30���i���j����Έ�����C���������k�̔�Вn��K�₷�邱�ƂɂȂ��Ă���B
JMAT�ɂ��Ă͊e�n�ŃI�[�o�[�t���[��ԂƂȂ��Ă��邪�A�����p�����K�v�ƍl���Ă���̂ŁA����A��Вn����̗v�]�����܂��Ĕh���̐��̌��������s���ӌ��ł���B
�J���e�A���Z�v�g�����ɔ����f�Õ�V�̐������@�ɂ��Č������s���Ă���B�܂��A��Вn�ɂ�����ی���Ë@�ւ̎w���ɂ��Ă͉��������肳��Ă���B
���ɂ��u�S�̃P�A�v�ւ̑�A��Ë@�ւ̕����x���A���ی��̏_��ȑΉ��AJMAT�̌p���x���Ɍ����đS�͂������đΉ�����B
�����k�����ǎw���č��ۂ̒����ے��A�����Îw���Ď��č���������
3��31���i�j��L����l������t��ق�K��A��Õی��S���̍����i�a�j��C�������Ή����܂����B
���k�����ǂƂ��Ă��A�����ۂɑ�����݂�24���ԑ̐��ŋƖ����s���Ă���A���ⓙ������ꍇ�͓��k�����Ǒ����ہi�d�b�F022-726-9260�j�ЊQ���{���֘A�������肢�������Ƃ̂��Ƃł��B
�܂��A�ی���Ë@�ւɑ���w���č����͏����������܂ł͑S�ĉ����Ƃ��A���݂͈�Ë@�ւ̑��Q�Ȃǂɂ��Ē������s���Ă���Ƃ̂��Ƃł���A����Ƃ�����t��Ɩ��ɘA�����Ƃ�Ȃ���A�Ɩ���i�߂čs���Ƃ̂��Ƃł����B
�Ȃ��A�ی��f�ÂɊւ���m�F�����͎��̂Ƃ���ł��B
�i1�j �k�Ђ̔�Q�҂�10����������ꍇ�A���ہA�Еۂ����m�łȂ��ꍇ�ł��u�s���v�Ƃ��Đ������ėǂ��i���ۂȂǂɁj�B�܂����҂���̐����A�Z���Ȃǂ����m�łȂ��ꍇ�ł��A��Ë@�ւ͑P�ӂ̑�3�҂ł���A��Ë@�ւɑ��Q���y�Ԃ��Ƃ͂Ȃ��B���̏ꍇ�́A�ی��҂�����ō�����U���邱�ƂɂȂ�B
�i2�j 3���f�Õ��ɂ��āA��Ђɔ����f�Ø^�A���Z�R���Ȃǂ��A�����Ȃǂ����ꍇ�́A�u�T�Z�����v���ł���B�ڂ������@�Ȃǂ́A3��30�����o�́u���k�n�������m���n�k�y�ђ��쌧�k���̒n�k�Ɋւ���f�Õ�V���̐����̎戵���ɂ��āv�i3��31���ɌS�s��t��ɑ��t�j�ɋL�ڂ��Ă���̂ŁA�������������B
�����k�n�������m���n�k�ɔ����J�Аf�Â̎戵���ɂ���
��L�ʒm���A3��29���t���ŋ{��J���ǘJ������J�Е⏞�ے����A�{�錧��t����ɔ��o����܂����B�{�����[��������܂����A�p���`�`���ƂȂ��Ă���d�v�Ȃ��ߌS�s��t��֒ʒm���Ă���܂��B
�{��J���ǃz�[���y�[�W�ihttp://www.miyarou.go.jp/touhokuoki/index.html�j�u���k�n�������m���n�k�ւ̑Ή��ɂ��āv�J����W 2011/03/28 �J�Еی��p���`�i�����J���ȃ����N�j�ɂ��f�ڂ��Ă���܂��B
�����k�n�������m���n�k�ɌW��ЊQ���������i��Ñݕt�j���ɂ���
���{��t�����A�W�L�ɂ��ēs���{����t����ɒʒm�����o����܂����̂ŁA3��31���t�ɂČS�s��t��ɒʒm���Ă���܂��B
�Ɨ��s���@�l������Ë@�\�z�[���y�[�W�ł��������������܂��B
http://hp.wam.go.jp/home/topics_list/recovery/tabid/947/Default.aspx
�����{��t�� ����s���ɂ���
���{��t����A4��11���ȍ~�̓������ψ�����܂ނ��ׂĂ̍s����\��ǂ���J�Â���|�̒ʒm������܂����B
������ÃZ���^�[�ł̑�����ː��ʂɂ���
�����a�@�@�\����ÃZ���^�[�ł�4��1���i���j���̑�����ː��ʂ�0.18μSv/hr�Ō��N�ɂ͉e���Ȃ����x���ł��B